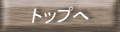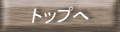私の旅日記〜2009年〜
金剛寺〜青梅〜

青梅市天ヶ瀬町に金剛寺という寺がある。

承平年中(931−938)、平将門が一枝の梅を地に挿し、仏閣を建立したのに始まるそうだ。
金剛寺山門

金剛寺表門

東京都指定有形文化財
製作は江戸時代初期であろうと推定されるそうだ。
金剛寺鐘楼

銅鐘は寛文6年(1666年)に寄進されたもので、青梅市指定有形文化財。
金剛寺本堂

青梅山無量壽院金剛寺
真言宗豊山派の寺である。
金剛寺の青梅は東京都指定天然記念物。
この梅は季節が過ぎても黄熟せず、落実まで青く、このため「青梅(あおうめ)」と称せられ、青梅市の名称もこれによって付けられたという。
青梅の地名の由るところの梅あり
機音や青梅は青蕾群れ
わずかばかりだが、花が咲いていた。

平将門が訪れた際、梅の枝を地面に刺したものが根づいたと言われているそうだ。
本堂の右手に庫裏がある。

庫裏の前に青梅句碑があった。

青梅やまたこのさきもいくちとせ 好々居臼左
好々居臼左は本名を横川好(よしみ)といい、明治初期の多摩地方俳諧宗匠として重きをなした人だそうだ。
明治28年(1895年)年5月、金剛寺住職杉本亮誉師建立。
枝垂れ桜の下に芭蕉の句碑があった。

梅か香にのつと日の出る山路かな
元禄7年(1694年)春、芭蕉51歳の句。
『炭俵』冒頭、志太野坡と両吟歌仙の発句である。
青梅句碑と同じく當山三十五世杉本亮誉師建立。
私の旅日記〜2009年〜に戻る