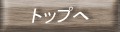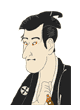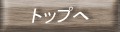私の旅日記〜2013年〜
唐崎神社〜唐崎の松〜
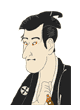
大津市唐崎に唐崎神社がある。

唐崎神社

滋賀県指定名勝 唐 崎 (唐崎神社境内)
唐崎は古くから景勝の地として数々の古歌などに取り上げられ、また、日吉大社西本宮にかかわる信仰や祭礼の場としても知られてきました。加えて「近江八景」の一つ「唐崎の夜雨」の老松との景観は、天下の名勝としてしばしば安藤広重らの浮世絵などにも取り上げられてきました。
現在、境内の中程に位置する松は三代目の松で大正10年に枯死した二代目の松にかわって、その実生木を近くの駒繋ぎ場から移植したもので、樹齢は150年から200年と推定されています。また、二代目の松は、天正9年(1581年)に大風で倒れた一代目にかわり、同19年に新庄駿河守らが良木を求めて植え替えたもので、幹周囲9メートルに及び、枝を多数の支柱に支えられた天下の名木として知られていました。今も境内の各所に残る枝を支えた石組みや支柱の礎石が往時の雄大さを忍ばせています。
現在の唐崎は、史上に見える景観ではないものの、湖上に突き出た岬状の地形と老松が織りなす景観は今なお優れており、その歴史的由緒と「近江八景」を具体的に体現できる数少ない場の1つとして貴重といえます。
なお、当地は平安時代からの大祓の場と考えられ、大津市の史跡にも指定されたいます。
滋賀県教育委員会
唐崎の松

「兼六園」の唐崎松は唐崎の松の種子を取り寄せて育てた黒松だそうだ。
芭蕉の句碑があった。

唐崎の松は花より朧にて
出典は『野ざらし紀行』。
「湖水の眺望」と前書きがある。
貞亨2年(1685年)、芭蕉42歳の句。
美濃大垣の常湖觀下天、建立。
元禄13年(1700年)、服部嵐雪は京から唐崎神社に参詣している。
京よりから崎へ詣るとて、しがの山越はするとなり。
志賀越とありし被(かつぎ)や菊の花
白井鳥酔は唐崎を訪れている。
○唐崎
樹下にたゝずみしはしは仰向てしけれるを見るさらに日影をもらさす夜の雨を思ひやられぬ交枝をさゝえてたてたる杖はかそえつきすまことに扶桑にも一つ松なるへし
唐崎や杖をちもとの散松葉
明和元年(1764年)9月、多賀庵風律は田子の浦の帰途、辛崎を訪れている。
行々て長等山をのそミ志賀の里を經て辛崎にいたる名高き峯々浦々蜆とる舩みな秋色
秋の日の暮れ所見む鳰の海
明和2年(1765年)、蓑笠庵梨一は唐崎の松を訪れて句を詠んでいる。
坂本の宿はつかれ足に長々と覚ゆるのみ、唐崎の松に到りて、はしめて風情は付ぬ。此日はとりわき小雨ふりて夜ならすとも称すへし。松の枝々はたた朦朧として、けにや花よりあわれに面白くは覚え侍る。
松風や朧を昼へ吹廻し
一茶の句がある。
辛崎の松はどう見た帰雁
『七番日記』(文化11年)
唐崎を三遍舞て帰る鴈
『八番日記』(文政3年)
辛崎は昼も一入夏の雨
『八番日記』(文政7年)
私の旅日記〜2013年〜に戻る。