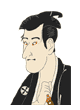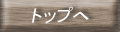私の旅日記〜2004年〜
鹽竈神社 〜志和彦神社〜
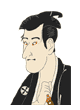
東北自動車道安達太良SAで安達太良連峰が見える。

安達太良連峰

中央が安達太良連峰の主峰安達太良山(あだたらやま)で、別名岳(だけ)山、またその形から乳首山(ちちくびやま)等ともいう。
安達太良連峰の最高峰は安達太良山(標高1,700m)ではなく、箕輪山(標高1,718.5m)。右に見えるのが箕輪山。
東北自動車道仙台南ICから仙台南部道路さらに仙台東部道路を行く。

仙台港北ICで国道45号に入り、塩竈へ。

むかし、左のおほいまうちぎみいまそかりけり。賀茂川のほとりに、六条わたりに、家をいとおもしろく造りて、すみたまひけり。かんなづきのつごもりがた、菊の花うつろひさかりなるに、もみぢのちぐさに見ゆるをり、親王たちおはしまさせて、夜ひと夜、酒のみし遊びて、夜明けもてゆくほどに、この殿のおもしろきをほむる歌よむ。
そこにありけるかたゐおきな、板敷のしたにはひ歩きて、人にみなよませはててよめる。
塩釜にいつか来にけむ朝なぎに釣する舟はここによらなむ
となむよみけるは、陸奥の国にいきたりけるに、あやしくおもしろき所々多かりけり。わがみかど六十余国の中に、塩竈という所に似たる所なかりけり。さればなむ、かのおきな、さらにここをめでて、塩釜にいつか来にけむとよめりける。
『伊勢物語』(第八十一段)
寛文2年(1661年)、西山宗因は仙台から塩竈を訪れた。
岩城をたちて六日にや、まだ朝霧のほどに、かの浦につきぬ。聞くならく、六十よ国の中々に詞を絶たり。河原のおとゞのむかしおもひやられて、かの朝臣の爰によらなんとながめしあまの小舟に乗て、霧のまがきのしまがへ(くカ)れなくさしめぐる。
浦山はいづくはあれどあま小舟かゝる所の秋の夕ぐれ
塩がまや色ある月のうす煙
島かくすそれしも霧の籬哉
カーナビの指示に従って、鹽竈神社(HP)へ。

鹽竈神社は表坂(男坂)という202段の石段を登るのだが、車は石段を登れない。急な坂道を登って駐車場に車を停める。
鹽竈神社

元禄2年(1689年)5月9日(新暦6月25日)早朝、芭蕉は石段を登って鹽竈神社に詣でた。
文治の燈籠

文治3年(1187年)7月10日、奥州藤原三代秀衡の三男泉三郎忠衡により寄進されたもの。
元禄9年(1696年)、天野桃隣は塩釜を訪れ、句を奉納している。
是ヨリ塩竈への道筋に浮嶋・野田玉川・紅葉の橋、いづれも道続なり。緒絶橋は六社の御前ニ有。塩竈六社御神一社に篭、宮作輝斗也。奥州一の大社さもあるべし。神前に鉄燈籠、形は林塔のごとく也。扉に文治三年和泉三郎寄進と有。右本社、主護より造営ありて、石搗の半也。
○法楽 祢宜呼にゆけば日の入夏神楽
享保元年(1716年)5月、稲津祇空は常盤潭北と奥羽行脚。鹽竈神社を訪れている。
六社明神に詣す。宮裏石壇の結構美を尽せり。泉ノ三郎寄進の鉄灯籠あり。又鉄の塩やき竈四ツあり。そのかみ此地にて塩を焼せ給ふといふ。今は塩浜しほやきなし。この竈の水を年々一度かゆれとも古代の水一杓つゝ残るゆへに万古不易の水とうとむへし。
塩かまは揚名の介風かほる
|
|
藻のひかり山もやとはす千賀の月
| 北
|
元文3年(1738年)4月、山崎北華は『奥の細道』の足跡をたどり、鹽竈神社を訪れた。
明神は當國第一の社なり。木立古り神さび。石の階百重に疊み上げ。樓門いよやかに構へ。廻廊緩く回り。社壇目出たく輝き。切れる石の中徑は。糸して引くが如く。細かなる敷る石は。洗へる大豆に似たり。石唐銅(からかね)の燈籠數も知らず。中にも和泉三郎寄進の燈籠は。形輪塔の如く珍らし。
元文3年(1738年)4月、田中千梅は鹽竈神社に参詣している。
猶たとり行ほと塩竃の浦に着日ハ午なりまつ大明神に詣す正一位一ノ宮塩竃大明神乃額ハ佐玄龍筆
寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で塩竈で句を詠んでいる。
宝暦5年(1755年)5月10日、南嶺庵梅至は鹽竈神社で「文治の燈籠」を見ている。
鹽竈明神を拝し和泉三郎の燈籠有宮立古く石壇高聳て斯る邊土に稀代なる粧ひ神器の塩釜四つ各水いろ等しからなはなし
宝暦13年(1763年)4月、蝶夢は松島遊覧の途上、塩竈を訪れている。
塩竈のやしろは結構つくせり。泉の三郎の奉納の燈籠に「文治三年」の文字ありありと、御釜の古雅なる、「禹の九鼎」とも伝べし。
明和元年(1764年)、内山逸峰は鹽竈神社に参詣している。
明る日はやく起出て、先塩がまの御社にまうでゝ見奉れば、おもひしよりはを(お)ごそかにして、宮居は三社ぞならび給ひける也。所のものゝいひ伝ふるは、此御神は、日の本にしてしほをやく事をはじめてをしへ給ひし御神なるよしをかたる。塩をやき給ひしかま也とて朽せず今に残りて有ける也。塩竈の御社にて、
やきそめしめぐみかしこし塩がまの残すけぶりや世々のにぎはひ
昔此塩釜の浦を夢にきたりて見し事を思ひ出て、
たどりきて遠きをしるや昔わが通ひし夢はちかのしほがま
明和6年(1769年)4月、蝶羅は嵐亭と共に鹽竈に泊った。