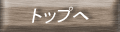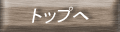2016年〜熊 本〜
通潤橋〜布田保之助〜

山都町大字下市の県道180号南田内大臣線に道の駅「通潤橋」がある。
通潤橋と白糸台地の棚田景観

平成20年(2008年)7月、重要文化的景観に選定。
通潤橋
布田保之助は、江戸時代末期の天保4年(1833年)〜文久元年(1861年)の約30年間の長きに亘り、矢部地域76ケ村の長で、行政の責任者であった(熊本藩の役職では「惣庄屋」という)人物である。
元来、布田家は、数代に亘り矢部地域の長を務めた家系であり、保之助の父、布田市平次も矢部の開発と人々の生活安定のため尽力していたが、保之助が8歳の時、36歳の若さでこの世を去っている。父の意志を継いだ保之助は、新田開発を目的とした用水路・ため池(堤)等の整備を行ったほか、道路や橋などの交通網を整備するなど、地域の実情に応じて数多くの開発事業を手掛けた。
現在、保之助が実施した事業として、
〈農業〉
| 用水・ため池(堤)
| 22か所
|
|
| 石磧(堰)
| 12カ所
|
|
〈交通〉
| 道路162か所、眼鏡橋
| 13か所
|
が知られており、矢部地域一帯で保之助の恩恵を受けない村はなかったと言われている。
布田保之助

このうち、保之助が実施した事業として最も有名なものが、白糸台地へ安定した農業用水を供給することを目的に建造された通潤橋・通潤用水である。通潤橋は、我が国で最大規模の石造アーチ水路橋であり、昭和35年2月に国の重要文化財に指定されたほか、平成26年9月に、国際かんがい排水委員会により初代の「かんがい施設遺産」として登録された。
また、通潤橋・通潤用水の完成以来、白糸台地一帯は、150年以上に亘り伝統的な水利用と農耕活動によって形成された景観が維持されていることから「通潤橋と白糸台地の棚田景観」として、平成20年7月に重要文化的景観に選定されている。
通潤橋

昭和35年(1960年)2月、国の重要文化財に指定。
放水は4月から11月まで、13時から約15分間行われるそうだ。
2016年〜熊 本〜に戻る