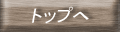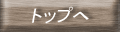私の旅日記〜2010年〜
金時山〜浅葱斑〜

今日は金時山に登ってみることにする。
足柄峠から金時山登山口の駐車場に車を停める。

駐車場からしばらく尾根道を行く。
浅葱斑(あさぎまだら)が飛んでいた。

雄山火口(おやまぼくち)。

キク科である。
撫子(なでしこ)

擬宝珠(ぎぼうし)

擬宝珠はユリ科。
金時山が見える。

鳥居が見えた。

ここから急な登りが続く。
山頂近くに赤花下野(あかばなしもつけ)が咲いていた。

天下の秀峰金時山

海抜1,213m。
かつては山の形から猪鼻嶽(いのはなだけ)と呼ばれていましたが、源頼光の四天王の一人坂田の金時が、この山で山姥に育てられたという伝説から、江戸時代の後期には金時山とも呼ばれるようになったようです。
あいにく霞んで眺望はよくなかったが、山頂に人が多いのには驚いた。
昭和13年(1938年)、斎藤茂吉は金時山に登ったようだ。
金時山
一方(ひとかた)は高萱にして一かたの木立のなだれ粗くあらしも
現なる眼下(ました)とほきを火をあげし山のなごりと見つるけふかも
霧うごくとばかりに香ごもりてあやしと思ふ谷あひ行くも
をやみなき雲に觸りさびしきまでに箱根の峡を見おろしにけり
身みづからこの山の上に居りにけり近きごと天つ日わたり時ゆくや
私の旅日記〜2010年〜に戻る