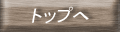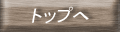私の旅日記〜2011年〜
配志和神社〜芭蕉の句碑〜

一関市山目に蘭梅山がある。

蘭梅山
太宰府に島流しにされた菅原道真の子敦茂が、当地に来山し父親が丹精こめて育てていた蘭麝梅の実を植えたところ当山一帯に咲き乱れ高貴な香りを放っていたので「蘭梅山」という名がついた。
蘭梅山の中腹に配志和神社がある。
今から約1800年位前、延喜式内社として、日本武尊(景行天皇の皇子)が奉ったのがはじまり。
延喜式内配志和神社参道

蘭梅山麓に二段式庭園がある。
二段式庭園の上段に「初音塚」があった。

此梅に牛も初音と鳴きつべし
出典は『江戸両吟集』。
今、この社殿の梅の盛りに鶯が鳴き出すのはもとより、牛までがきっと鳴くにちがいない。
延宝4年(1676年)、芭蕉33才の句。
モミ林の中を石段が続く。

配志和神社社殿

「本殿養和元年(1181年)9月16日改築、拝殿正徳元年(1711年)9月16日改築」とある。
一関市指定文化財である。
御祭神は高皇産靈神・瓊瓊杵尊・木花開耶姫命。
社殿の左手に「梅香塚」があった。

梅か香にのつと日の出る山路かな
『炭俵』冒頭、志太野坡と両吟歌仙の発句である。
早春の薄明の中、山路を登って行くと、野の梅の香が強く薫っている。と急に、あたりを赤々と染めて、朝日が昇ってきた。
元禄7年(1694年)、芭蕉51才の句。
天明6年(1786年)4月11日、菅江真澄は配志和神社に参詣している。
十一日 大槻の屋戸よりはいといと近き配志和神にまうづ。杜の梢は花ちり若葉さし、まだ咲やらぬかた岨の木々もめづらし。鳥居の額は土御門泰邦卿の真蹟(カキ)給ひしといふ、手風(テブリ)ことにめでたし。そもそも此神社(ミヤシロ)は、斎(イツキ)奉(マツ)りしよしを云ひ伝ふ配志和ノ社ノ内(カンサネ)は皇孫彦火瓊々杵ノ尊、左方(ヒダリ)は木花開耶姫命、右方(ミギ)は高皇産霊尊也。また明神ノ御社(ミヤシロ)をはじめ八幡ノ社、鎌足ノ社、安日ノ社、神星ノ社、土守ノ社、かゝるみやしろみやしろにぬさとりくまぐま見ありくに、菅香梅とて、よしある梅も青さして、こゝにも老婆(ウバ)杉とて千年(チトセ)ふりけむ、枝のなからに山桜の寄生(ヤドリキ)ありて花いたく咲たり。なほ木のもとにふりあふぎて、
いつまでもちらでや見なむ杉が枝の花もときはの色にならはゞ
「私の旅日記」〜2011年〜に戻る