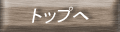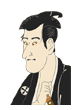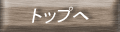私の旅日記〜2015年〜
津幡城跡〜河合見風の句碑〜
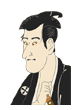
津幡町字清水の高台に津幡小学校がある。

津幡城跡である。

津幡城跡
寿永2年(1183年)の源平合戦の折、倶利伽羅の一戦を前に、平維盛配下の平家軍が津幡に布陣し、街道を見下すこの地に砦を設けたといわれている。
天正4年(1576年)上杉謙信が越中より侵入した際に津幡に布陣し、七尾城を平定する足掛かりとしたと伝えられている。
天正11年(1583年)前田利家の支配するところとなり、越中に対する備えとして城を築き、弟の秀継に守らせた。
翌12年佐々成政の末森攻めの際に、利家は秀継と共に末森城救済の軍議をここで開いている。
その後、利家が加賀・能登・越中三国を支配するようになると、この城は必要性を失い廃城となった。
津幡町教育委員会
河合見風の句碑があった。

はつなすびそれから花のさかりかな
昭和42年(1967年)4月、建立。
蕉門三世 河合見風 句碑
見風は通称を理右衛門といい、正徳元年(1711年)に生まれ、家業の米穀商と旅籠を営むかたわら俳諧を学び、世の人々から「俳諧の長者」と称せられた。
また、ひろく諸国の俳人と文通し、金沢の並木町に草庵を構え、特に加賀藩の重臣前田土佐守直躬(なおみ)と親交があった。
見風の文化的偉業としては、倶利伽羅山猿ヶ馬場にある芭蕉の句碑「寝覚塚」や越中氷見の「有磯塚」の建立、そして明和2年(1765年)の「為広塚」再建などがあげられる。
天明3年(1783年)、73歳で没し、北中条の本福寺にある累代の墓地に葬られた。
津幡町教育委員会
隣に「為広塚」もあった。
私の旅日記〜2015年〜に戻る