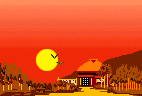古人各自筆ヲ用翁之手跡ハ岩瀬郡須賀川諏訪之社ニ
|
有写之各像ハ辰之浦翁ハ古図ヲ写旧化書
|
|
うらみせて涼しき瀧の心哉 桃青
|
「奥の細道碑」について
『宗祇戻』(柿衛文庫蔵)は、宝暦4年(1754年)、白河の俳人和知風光が編集した俳句の本。挿図に松尾芭蕉の肖像と諏訪明神(神炊館神社)に奉納されていた芭蕉真筆の句として
「うらみせて涼しき瀧の心哉」
に説明を加えて掲載しています。
(この句は岩波版芭蕉俳句集)(492)、加藤楸邨『芭蕉全句』(525)に収録されています。
『曽良随行日記』(天理大学図書館蔵)は、元禄2年(1689年)、松尾芭蕉の『奥の細道』の旅に随行した弟子の河合曽良が書きとめていた日記。須賀川には4月22日から29日まで滞在しました。碑に刻まれているのは、28日諏訪明神に参詣した時の一節です。
廿八日 発足ノ筈定ル。矢内彦三郎来而延引ス。昼過ヨリ彼宅ヘ行而及暮。十念寺・諏訪明神ヘ参詣。朝之内、曇。
三基の石灯篭は、芭蕉が参詣した元禄年間に当神社に奉納されたものです。
総鎮守神炊館神社
元禄2年4月26日、芭蕉は須賀川から江戸の杉山杉風に書簡を送付したが、その折、次の句を記す曽良の書簡が添付されているそうだ。
日光うら見の瀧
|
|
ほとゝぎすへだつか瀧の裏表
| 翁
|
|
うら見せて涼しき瀧の心哉
| 曽良
|
神炊館神社本殿

元禄9年(1696年)7月、天野桃隣は『奥の細道』の跡をたどる旅の帰途で須賀川に2泊、諏訪明神へ参詣して句を詠んでいる。
須ヶ川に二宿、等躬と両吟一卷満ぬ。所の氏神諏訪宮へ参詣、須田市正(いちのかみ)秀陳饗応。
○文月に神慮諫ん硯ばこ
諏訪神社近くに石井雨考が住んでいた。
『奥の細道』〜東北〜に戻る

|