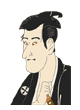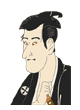今年の旅日記
川原町〜芭蕉像〜
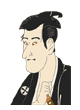
長良川温泉「十八楼」から川原町を歩く。
「十八楼」の前に芭蕉像があった。

俳聖・松尾芭蕉翁は生涯に何度も美濃の国を訪れています。
江戸中期貞亨5年(1688年)芭蕉翁が岐阜を訪れた際、長良川畔にあった水楼を「十八楼」と名づけ、かの有名な「十八楼の記」を記しました。このことは地域にとってもかけがえのない誇りとなり、子に孫に語り継がれておりました。それから170年余経た江戸時代末期、この誉れが忘れ去られていること悲しんだ当館の先祖が、地域の宝を再興しようと一念発起し、万延元年(1860年)に自らの旅館の名前を「山本屋」から「十八楼」に改名しました。
時を経てなお、芭蕉の感嘆した景色と変わらぬ美しい自然に囲まれた情緒ある町を守り継ぎたいと願っています。
川原町の家並

川原町(湊町・玉井町・元浜町)の由来
斎藤道三・織田信長のころ(16世紀中頃)から、このあたりは中川原(明治初期には富茂登(ふもと)村)と呼ばれ、市場が開かれ、商業の拠点として繁栄していたようです。
道三は城下町をつくるにあたり、ここから上にかけての場所に川湊(かわみなと)を設け、長良川の上流域で豊富に産する美濃紙・木材・茶などや当時のブランド品であった関の刃物を、ここを中継地にして全国各地に売りさばいたとも考えることができます。
江戸時代になると、尾張藩がここを治め、長良川役所が置かれました。ここを下る荷船から船役銀(ふなやくぎん)(通行税)を徴収しました。荷の種類は竹皮・酒・灰・炭・紙・木・茶・米など多様でした。それらを取り扱う紙問屋・材木問屋などが軒を連ねていました。いまでも当時の商家を偲ばせる格子造りが残っています。軒屋根に設けられています屋根神様は町内を火災から守る秋葉様です。
珍しいところでは、明治の頃の古い銀行の建物もあります。また、道三の子斉藤善龍が建立した禅宗寺院の伝燈護国跡には、庚申堂が建てられています。昔の面影がただようこの地域の散策は、鵜飼情緒をさらに高めてくれます。
川原町まちづくり会
格子造りの家

株式会社「藤華」

川原町広場に「連句碑」があった。

貞享五戌辰林鐘十九日
|
於岐阜興行
|
|
蓮池の中に藻の花まじりけり
| 芦文
|
|
水おもしろく見ゆるかるの子
| 荷兮
|
|
さゞ波やけふは火とぼす暮待て
| 芭蕉
|
|
肝のつぶるゝ月の大きさ
| 越人
|
|
苅萱に道つけ人の通るほど
| 惟然
|
|
鹿うつ小屋の昼はさびしき
| 炊玉
|
|
真鉄ふくけぶりは空に細々と
| 落梧
|
|
かし立岨の風のよめふり
| 蕉笠
|
|
古寺の瓦葺たる軒あれて
| 己百
|
|
夜る夜るちぎる盗人のつま
| 梅餌
|
|
なみだより雨にしめりし蓑おもく
| 露蛩
|
|
馬の乗たる舟のせばさよ
| 鴎歩
|
|
須磨明石見残すほどに暑くなり
| 拾景
|
|
筆ゆひかぬる茄子ちひさし
| 角呂
|
|
蓬生の垣ねに機を巻かけて
| 東巡
|
|
| 下略
|
平成27年(2015年)8月、岐阜県俳句協会創立20周年に建立。
貞亨5年(1688年)の夏、松尾芭蕉は岐阜に逗留し、鵜飼を観覧したり連句を巻いたりした。この作品は地元はもとより、名古屋や関からも連衆を迎えて興行された十五吟による五十韻で、佐野芦文編の『つばさ』に収められている。
貞亨5年(1688年)6月19日、芭蕉は荷兮・越人・落梧らと岐阜で連句興行。
宝永3年(1707年)、『つばさ』(美濃蘆文撰)刊。