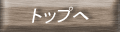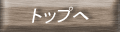私の旅日記〜2011年〜
二本松城〜二本松少年隊〜

二本松市郭内にある二本松城へ行ってみた。

ふくしま緑の百選
霞ヶ城とカサマツ
昭和60年6月選定
主唱/福島民報社・福島県緑化推進委員会
二本松城は日本100名城の一つ。
箕輪門

昭和57年(1982年)、再建。
城壁

二重櫓が見える。
本丸石垣

天守閣はない。
二本松城の歴史
二本松城は、室町時代中期に奥州探題を命じられた畠山満秦が築造し、以後畠山氏歴代の居城として、140年余り続きました。その後天正14年(1586年)、伊達正宗の南奥制覇のために落城しました。
豊臣時代になると、二本松城は会津領主となった蒲生氏郷の重要な支城として、中通り(仙道)警備の任を与えられました。二本松城に石垣が積まれ、近世城郭として機能し始めたのはこのころだと推定されます。
その後、徳川時代初期も会津領として、上杉氏、蒲生氏、加藤氏らの支配下にありました。
とくに、加藤氏支配時代には本丸を拡張したことが石垣解体調査で確認されました。
二本松藩が誕生した寛永20年(1643年)、初代藩主丹羽光重が10万700石で入城し、幕末まで丹羽氏10代の居城として、220有余年続きました。戊辰戦争に際し、西軍との徹底抗戦で城内・家中屋敷のすべてを焼失し、慶応4年(1868年)7月29日に落城しました。
丹羽光重は織田信長、豊臣秀吉に仕えた丹羽長秀の孫。白河藩から二本松藩へ移封された。
寛政3年(1791年)6月2日、鶴田卓池は二本松を訪れている。
二日 壱り三十壱丁 二本松
城主 丹羽加賀ノ守 十万石
奥州探題・畠山氏居城霞ヶ城址

当記念碑は、昭和28年(1953年)に施工された本丸入り口石垣修復を記念として、奥州探題・畠山氏末裔である二本松氏により、昭和30年に入り口左側に建立されました。
平成7年(1995年)本丸石垣修築復元工事の完成に伴い、当所に移設しました。
二本松市
搦手門跡

城の裏面にあたる門のことで、現在は石垣および門柱を建てた礎石を残すばかりです。この門は、二本松城始築時の慶長初期(1590年)頃に建てられ、その後に何度か修築されたことが絵図等でわかります。
一般的に、城は敵に対する正面(大手)の防備は堅固ですが、裏面(搦手)はそれに比べて弱いところから、この語の起源になっています。
二本松市
二本松少年隊顕彰碑

この一帯の平坦地は「少年隊の丘」と呼ばれ、戊辰戦争直前まで砲術道場で学ぶ少年たちが稽古を行った場所といわれています。
当碑は、昭和15年(1940年)の紀元2600年記念事業にあたり、戊辰戦争に出陣した少年隊士の顕彰を目的に、町一丸となってこのゆかりの地に建立したものです。
碑表面は、旧二本松藩主丹羽家16代当主・丹羽長徳の揮毫、碑裏面には隊長・木村銃太郎、副隊長・二階堂衛守をはじめ、出陣した少年隊士62名の氏名が刻まれています。
二本松市
二本松城に「智恵子抄詩碑」の碑がある。
「私の旅日記」〜2011年〜に戻る