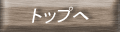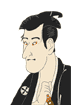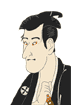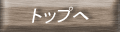今年の旅日記
番町小学校〜子規「旅立ちの像」〜
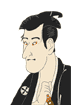
松山市二番町の番町小学校に子規「旅立ちの像」があるというので、行ってみた。
子規「旅立ちの像」

箱根の山の踏破を目指して草鞋の紐を結ぶ姿です。
明治5年(1872年)10月、巽学校(大街道)・勝山学校(一番町)・智環学校(末広町)設立。
明治13年(1880年)、正岡子規は勝山学校を卒業。
明治20年(1887年)4月、温泉郡外側尋常小学校創立。
明治25年(1882年)10月3日、子規は新橋から大磯までの旅をする。
昭和53年(1978年)3月25日、卒業記念に虚子の句碑を建立。
昭和61年(1986年)11月、創立100周年行事で子規「旅立ちの像」除幕。
右に子規の句碑があった。

國なまり故郷千里の風かをる
明治26年(1883年)の句。
『子規全集』(第一巻)「寒山落木二」に「松山会」として所収。
左には高浜虚子の句碑があった。

春風や闘志いだきて丘にたつ
『五百句』に「大正二年二月十一日 三田俳句会。東京芝浦。」とある。
今年の旅日記に戻る