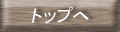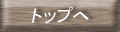私の旅日記〜千葉〜
補陀落山那古寺〜多宝塔〜

館山市那古の高台に補陀落山那古寺がある。

新義真言宗智山派の寺である。
那古観音は関東八十八ヵ所霊場56番札所でもある。
仁王門

明治39年(1906年)8月10日、河東碧梧桐は那古観音を訪れた。
那古の観音は形勝の地を占めた山の中腹に在る。山門の下に蓆を敷いて一人の盲目尼が坐っておる。
仁王像

| |

|
鐘楼

阿弥陀堂

鎌倉時代造立で、県指定有形文化財。
阿弥陀如来坐像も県指定有形文化財。
多宝塔

宝暦11年(1761年)創建で、県指定有形文化財。
本堂(観音堂)

県指定有形文化財
銅造千手観音坐像は鎌倉時代の作で、国指定の重要文化財。
文明18年(1486年)、道興准后は那古観音に詣でている。
那古の観音にまうで、ぬかづき終りて、夕の海づらをながめやるに、寺僧の出で来て、あれ見給へ、入日を洗ふ沖津白浪とよめるは此の景なりといへり。されど、それは津の国住吉郡なごの浦をよめるとかや。そのなごの浦に難波津をまもれる人の住みしによりて、其の浦を津守の浦といひ、又、子孫の氏によびて津守氏ありとかや。今はなごの浦の所に、さだかにしれる人なしとなむ。此の歌いづちにしてよめるもしり難けれど、寺僧のいふに任せてしるすものなり。まことに今も入日を洗ふ沖つ波、眼前の景色えも言ひがたし。
なこの浦の霧のたえまに眺むればこゝにも入日洗ふ白浪
「入日を洗ふ沖津白浪」は後徳大寺左大臣の歌。
なごの海の霞の間より眺むれば入る日を洗ふおきつしらなみ
『新古今和歌集』
本堂(観音堂)の手前に芭蕉の句碑があった。
芭蕉の句碑

春もやゝ氣色とゝのふ月と梅
明治22年(1889年)4月、芭蕉二百回忌に稻原路米建立。
稻原路米は那古町稻原(現館山市小原)の山口茂兵衛。三世雨葎庵文酬に俳諧を学び、四世雨葎庵を嗣号。一澄に挿花を学んでいる。
本堂(観音堂)の奥にも芭蕉の句碑があった。
芭蕉の句碑

此のあたり眼に見ゆるものは皆すゝし
文政6年(1823年)、建立。
碑陰に「当国世話人」として「文守」「里遊」の名が見える。
『杉間集』配本扣に「山本 高木元生 文守」「末吉 松崎清吉 里遊」とある。
青空や空や葉月の天の河
| 文守
|
|
行雁に来るや南部の子牽牛
| 里遊
|
大黒堂

宝暦10年(1760年)、露柱庵に滞在中の鳥酔は那古寺に遊ぶ。
那古千手堂上 別当補陀落山那古密寺 坂東三十三所終
御詠歌 ふたらくやよそにはあらしなこの寺
岸うつ波を見るにつけても
静さや浪の浄土の秋の風
文化12年(1815年)11月27日、小林一茶は補陀落山那古寺を訪れている。
[廿]七 晴 久保ニ入 夜少雪 補陀洛山那古寺
『七番日記』(文化12年11月)
文化14年(1817年)4月、一茶は再び補陀落山那古寺を訪れたようである。
那古山
おのれ迄二世安楽か笠の蠅
『七番日記』(文化14年4月)
大正10年(1921年)11月19日、与謝野寛・晶子夫妻は白浜・奈古へ旅をする。
那古寺の建立を待つもののごと十三人が鳩とたはぶる
凡骨と云ふ人の撞く普陀洛の鐘と知らざる那古の浦人
那古寺の普請の瓦まゐらせず海に比べて醜きがため
唯聴かず鏡が浦を行く船にものも云ふべき潮音の台
那古寺の湖音台に題すらくここより海へここより天へ
『草の夢』
昭和9年(1934年)2月19日、与謝野晶子は那古寺を訪れている。
波しろし那古船形の御堂をば牙あるものの護る海とも
朱なれども海にひかれて光るなり那古の御堂は金鱗のごと
二婦人が車中の作を書ける見て更科日記を思ふ國かな
「いぬあじさゐ」
「私の旅日記」〜千葉〜に戻る