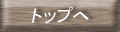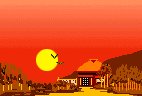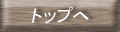私の旅日記〜2005年〜
千葉寺〜千葉笑〜
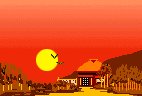
京成千原線千葉寺駅で下車。

大網街道沿いに千葉寺がある。
千葉寺は真言宗豊山派のお寺で、山号は海上山。
和銅2年(709年)、創立。開基は行基菩薩。
坂東三十三観音霊場29番札所、関東八十八ヵ所霊場47番札所でもある。
仁王門

仁王門の裏から写真を撮る。

仁王門は文政11年(1828年)の建築。
鐘楼の桜

千葉寺境内
縁起では和銅2年(709年)東国巡錫中の行基が池田郷の池で千葉(せんよう)の青蓮に霊を感じ、丈六の十一面観音像を刻み、その話を聞かれた聖武天皇の勅命により堂舎を建立(東方約1kmの観音塚と伝えられる)し、海照山歓喜青蓮千葉(せんよう)寺と称したという。永暦元年(1160年)雷火で伽藍を焼失し、現在地に移転する。この頃より千葉氏の厚い信仰を受けるようになったと伝えられています。
千葉市教育委員会
大きな公孫樹の木があった。

千葉寺ノ公孫樹
この大きなイチョウは、和銅2年(709年)、僧行基がもたらしたものと伝えられる。樹高30m、目通り8mもあり、神奈川県鎌倉市の「鶴岡八幡宮のイチョウ」よりも大きい。樹勢旺盛で3mから枝を張り、乳柱がたれているがこれを煎じて飲むと母乳がよく出るようになると伝えられている。
千葉市教育委員会
千葉寺には「千葉笑」と呼ばれる奇習伝承を残している。
また千葉笑とて、としごとのしはすのつごもりの夜、里人この寺によりつどひ、各おもておほひして、地頭・村長などの邪曲(よこしま)事よりはじめ、人のよからぬふるまひどもをあげつらひのゝしり合ふことありといへり。こは人々のおこたりをいさむるわざなれば、筑波嶺のかゞむなどには、いといとまされる風俗(ならはし)といふべし。
千葉寺や隅に子どももむり笑ひ
小林一茶(文政6年)
文化14年(1817年)6月27日、一茶は江戸を発ち、7月4日に柏原に帰着。これを最後に一茶は江戸を訪れることはなかった。
私の旅日記〜2005年〜に戻る