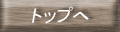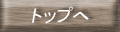尾張の国にすきの駅を去こと一里はかり、南春日井原のすへに小川あり。西行渡と呼へり。いつの昔にや、西上人杖をこゝにとゝめて尾花かくれの菴を結ひみつから肖像を彫刻し給ふよし、この處の詠歌なりとて今も古俗の口に傳ふ。星霜うつりて、西行堂のみ形斗川添にありけるも、夫さへ洪水のために流れうせぬ。数百年の後、この川下なる比良村といふ處にて、芦苅ける泥中より、かの肖像を得たりしを、程過て府下の史星野某これを請得たまへり。それより隠士白梵庵に与ふ。これを市邊生に傳へて、宝暦の末には城南の今平庵にさし置けるを、小牧なる臥雲叟、布毛和尚なと請求めて、かの古跡に一宇を造立の志ありけるに、彼遺跡はすかれて桑田となり、尺地の營も及ひかたしとて、天明のはしめ其あたり一の久田といへるかた里に閑地を卜して安置しありけるを、わか里春日井はらは往古このゆかりもありて、かの遺跡もあしかきのまちかく隣れはと、社中の誰かれより会ひて、彼肖像をこひもとめ、僕が家のかたはらに茅舎を結ひ、櫻をうゑ流を堰いれて、永く上人の光をとゝむることにはなりぬ。
文化八のとし辛未の春 得芝しるす。
『木瓜つゝじ』 |
得芝は松田丞政。
天保6年(1835年)4月10日、56歳で入寂。
得芝没後、本光寺に復帰した。
得芝の父宇梅は正念寺境内に芭蕉ゆかりの穂麥塚をいとなみ、「来与に穂麥喰はん草枕」の芭蕉の句を刻んでいる。
|
本光寺に「西行法師木像」が安置されているそうだ。
本堂の右手に臥雲の句碑があった。

唖となる果はしらずや蝉の声
臥雲は本光寺の住職。
臥雲の句碑の左手に鯉圭の句碑があった。

道志登ふ是世も長き月日かな
鯉圭は横内の人。丹羽忠次郎氏兼といい、飛車寓と称した。臥雲一門の俳人。藤蔭舎。
|
「芋塚」句碑の台石に「鯉圭」の名がある。
小牧市大山の不動堂にも鯉圭の句碑があるようだ。
尊ふとさや石に不動の苔の花
2014年〜愛 知〜に戻る